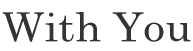 |
| 「初めまして。河野 紗江です」 高校1年の夏。私は、転校した。 一面を森に囲まれたこの地域に、都会とは言えないまでも、大きな街で育ってきた私はまだ戸惑いを隠せない。 家から近くのコンビニまで、なんと一時間近く歩かなければならないのだ。 不便なのは言うまでもなく、また、この地域の人達ののんびりとした雰囲気にも馴染めずにいた。 「じゃあ、河野の席は一番後ろの空いている場所な」 担任に案内されて、席に着く。 クラス中の好奇の目が、チラチラと感じられた。 そのまま、HR、一時間目、二時間目と、時は過ぎていく。 しかし私はまだ誰とも話す事が出来ずにいた。 まぁ、誰かが話し掛けてくれるだろう。そんな人任せな考えが甘かったのか、それとも、気まずくて机に顔を伏せていたのが悪かったのか。 結局この日はクラスの交流を0にしたまま、家路に着いたのだった。 「ただいまー!」 玄関の引き戸が、ガラガラと音をたてる。 売家だったこの家を買い取ったのだが、なんとも古い家なのだ。その分、広いので文句は言えないが…。 「おかえりなさい。どうだった?学校」 山積みにされたダンボール箱を片付けながら、母が聞いてくる。 「うん、まぁまぁかな」 友達が一人もできなかった。などと言えず、曖昧な返事をした。 「そう、それは良かったわ。そうだ、コレお隣さんに持っていってくれない?」 忙しそうな母を見、特に断わる理由も無かったので、渋々頷いた。 渡された袋の中には、小さな箱が入っている。石鹸か何かだろう。 「行ってきます」 お隣さん。とは言うものの、百メートルは軽く離れている。 私は整備されていなくて歩きにくい道を、転ばないよう気を付けながら歩いた。 「ごめんくださーい!」 今時、インターホンの無い家があるなんて… 何処を探しても、ボタンが見付からないので、仕方なく声を張り上げる。 少し不機嫌さを纏った声が、畑ばかりのだだっ広い景色に溶けて消えた。 「はいはい、どちら様?」 出てきたのは、おばあさん。八十代、と言った所だろうか。 「あの、隣に引っ越してきたので、挨拶に」 これからよろしくお願いします。と、ありきたりな文句を並べて、袋を差し出した。 「あら、ありがとう。あ、貴方。あの子に会ったら、宜しく伝えてちょうだいね」 やんわりとした笑顔を見せて、おばあさんは家の中に引っ込んでしまった。 あの子? 孫でも、いるんだろうか。 この地域には、小学校と、中高一貫の学校がそれぞれ一校ずつしかないから、そこに通っているのかもしれない。 あーだこーだと考えながらの帰り道。 「こんにちは」 いつの間にか、目の前に女の子が立っていた。 私と同い年くらいだと思う。 「あ、どーも」 実は私は人見知りをするタイプなのかもしれない。 我ながら、愛想が無いなと思った。 「私は、ヒカリ。貴方は?」 「…紗江」 無愛想な態度も気にせず、彼女はフフフッと可愛らしく笑った。 「ねぇ、サエ。知ってる?」 と、初対面にも関わらず、彼女は話し出す。 その内容は、あそこのおばさんはケチだとか、あの畑のトマトは美味しいだとか。 そんな他愛ない物だったけれど、自然と打ち解ける事ができた。 「ねぇ、また会える?」 私が問うと、 「うん、また会いに来る」 彼女は、当たり前、と言うように、頷いた。 こうして唐突に、初めての友達ができたのだった。 はぁ。 登校3日目の帰り道。 私は、一人、憂鬱な気分だった。 相変わらず、クラスメートとの会話が無いのだ。 休み時間や昼食時に一人でいる私を盗み見ている人達に、話しかけてよ。なんて、理不尽な怒りすら覚えてしまう。 自分から、話しかける勇気なんて無かった。 こんな事で悩むなんて、思ってもみなかった。 前は、どうやってコミュニケーションを取っていたっけ。 転校前の自分の生活に思いを馳せてみるも、結局たいした成果は無かった。 「サエ?」 顔を上げると、ヒカリがいた。 初めて会った時もそうだが、彼女は本当に突然現れる。 ヒカリは私と同い年だが、学校には通っていないらしい。 「大丈夫? サエ」 背中にくっついている負のオーラを感じ取ったのか、彼女は聞いてきた。 「何でもないよ。ヒカリは、元気?」 心配させない為ではなく、単に意地を張ってるだけだ、ということは自分でも分かっている。 「私は…寂しい」 ヒカリは呟いた。 〝寂しい〟 私が強がって言えなかった言葉を、ヒカリはいとも簡単に口にする。 自分が至極子供に思えた。 「大丈夫だよ、ヒカリ。私がいる」 私も寂しいから、仲間だね。そう教えてあげると、ヒカリは嬉しそうにニコッと笑った。 「サエ、良い所に連れて行ってあげる」 返事をする前に、既に私の腕を引っ張って進んでいくヒカリ。 鬱蒼とした森を器用に進んでいく彼女の後ろを、一生懸命着いて行くと、 「着いたよ、サエ」 不意にヒカリが振り返って、そう言った。 目の前には、小さな湖。人気は、全く無かった。 「すっごいキレイ…!」 私は毎日此処にいるの。と、空を見上げながらヒカリが言う。 「人、いないね」 「此処には、洋ちゃんと私しか来ないよ」 今日からは、サエもいるね、と嬉しそうに彼女は笑声を上げた。 「ヨウチャン?」 「そう、目がね、クリクリしてる子」 それだけじゃ分かんないよ、と言いつつ、勝手にヨウチャンを想像してみた。 頭の中で、ヨウチャンがニッコリと笑う。 いつか、本物に会ってみたいなと思った。 「ねぇサエ、練習しよ?」 彼女はぴょんと跳ねて、私と向かい合わせになるようにして立った。 何の? と、目で問うと、 「友達作り!」 そう言ってまたニコッと笑うのだった。 私はただただ目を丸くするばかり。 突拍子も無い事を言われたからではなく、何故友達がいないとバレたんだろう、という疑問からくる驚きだった。 「あははっ、サエ、変な顔! ね、するでしょ? 練習」 するよね? と、もう一度言われて、ほぼ強制的に頷かされた。 練習。とは言っても、なんてことはない。 唯ヒカルと話したり、笑ったり。 水の中を覗いたり、花を摘んだり。 楽しむだけなのだ。 それでも何故か、明日はこの調子で皆に声を掛けることができる気がしてくるのだった。 「もう大丈夫だね、サエ。明日はきっと楽しくなるよ」 ヒカルが言うと、妙に納得してしまう。 「ありがとう、また明日!」 ヒカルは何も言わずに、手を大きく振っていた。 相変わらず笑顔で、〝寂しい〟と呟いたあの面影は、どこにも無くなっていた。 「お、おはよう!」 シン…と、教室が静まり返った。 出だしが肝心だからと、ありったけの声を出して、挨拶をしてみたのだが、失敗だっただろうか。 そう思うと、恥ずかしさと、心細さで泣き出しそうになった。 「河野さん、おはよう!」 そんな私に、一人の女の子が挨拶を返してくれた。 それに釣られるように、周りから、おはよう、と聞こえてくる。 「返事、してくれないかと思った…」 思わず零れた弱音に、 「あはは。違うよ、河野さんがあまりに大きな声で挨拶するから、ビックリしただけ」 傍にいた女の子は、親切にもそう教えてくれ、その言葉に赤面する私に、でも、河野さんって実は面白い人なんだね、と言ってくれた。 それからは、皆が口々に“話しやすい人で安心した”と言ってきた。 どうやら私は、人を近づけない雰囲気を無意識のうちに出していたらしい。 周りに話せる人がいるというものは、こんなにも嬉しいことだったのか、と気づかされた。 「ヒカリー?」 学校が終わって、真っ先に向かったのは、昨日教えてもらった湖。 いつも此処にいる、と確かにヒカリは言っていた。 でも、どこにも姿が見えないのだ。 ガサガサッ 傍の草が、不自然に揺れた。 「……ヒカリ?」 振り向くと、そこに立っていたのは、おばあさんだった。 何処かで見たことあるな。と思って、良く考えてみると、なんてことは無い、お隣のおばあさんだ。 「ヒカリを、探しに来たのかい?」 前も見たやんわりとした笑みを浮かべて、尋ねてくる。 「ヒカリを、知っているんですか?」 ええ、と少し寂しげに笑う。 「私もね、よく遊んだのよ。貴方と同じ位の時に」 そんなはずはない。 だってこのおばあさんは、最低でも七十を過ぎている。 「ヒカルはね、昔からずっと此処に住んでいるの。ある日突然見えなくなってしまったけれど、確かにいるのよ」 「ヒカルは、人間じゃないの?」 大して驚いていない自分がいた。 「あの子は、自分と似た雰囲気の人間にしか、見えないわ」 憶測だけれどね、と付け加える。 「私は、ヒカルとは似ていない」 ヒカルは、明るくて、元気で。 私とは、似ても似つかない。と思った。 「いいえ、似ているわ。初めて会ったとき、ヒカルに似た寂しい目をしていたもの」 “あの子に会ったら、宜しく伝えてちょうだいね” そう言われた事を思い出した。 「ヒカルは、今も此処にいるの?」 きっともう、ヒカルの姿を見ることは無いのだろう。 昨日、“また明日”と言ったときに、何も言ってくれなかったことが、その証拠だと思った。 「ええ、だから私も良く此処に来るの」 “此処には、洋ちゃんとヒカリしか来ないよ” 頭の中で、ヒカリの声が聞こえた。 「もしかして、ヨウチャン?」 そう呼ぶと、おばあさんは、ハッとして此方を見てきた。 「懐かしいわ、その呼び方」 彼女もきっとヒカリに会いたいんだろう。 「もし、失礼でなければ、ヨウチャンって呼んでもいいですか?」 ええ、ええ。と、ヨウチャンは何度も何度も頷いた。 ねぇ、ヒカリ。 貴方の言った通り、今日は楽しい日になりました。 もう私には見えないけれど、きっと貴方は今も私とヨウチャンの隣で笑っているんでしょう? あの、人懐っこい笑顔で。 色々とお世話になったけれど。 私は大して何もしてあげられなかったと思います。 でも、少しでも。 少しでも、貴方の寂しさを和らげてあげられたなら、それで良いや。そんな風に感じるのです。 風邪が、優しく頬を撫でる。 夏草の独特な香りが、ふわっと鼻をくすぐった。 “サエ、洋ちゃん!” 隣で、ヒカリが笑った気がした。 by 楠木架音 |